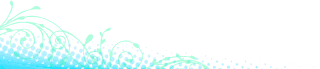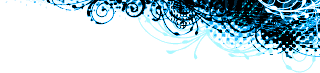
「ライドウちゃん、今お帰りかい?」
にこにこと何かの入った鍋を手に立つ中年女性は、なにくれとなくライドウを気遣ってくれる人だった。
「ああ……まあ」
曖昧に返事をしながらも、困ったように思わずゴウトに目を移す。
人付き合いは苦手だと言うのに、何故か話しかけられる。
ゴウトは知らん顔をしていた。
「今、行こうと思ってたから、丁度良かったわあ」
はい、と鍋を手渡され、狼狽える。
「お豆腐、お裾分けよ。ライドウちゃん、きちんと食べてる?全く痩せっぽっちなんだから……あ、この間の肉じゃがのレシピ、書いたから。はい、持っていってね」
次々と繰り出される言葉に対応仕切れぬまま、両手が塞がっちゃってるわねと外套を捲り、学生服の衣嚢にぐいとそれを突っ込まれた。
「……ありがとうございます」
いつもながら、それだけ言うのが精一杯であった。
「じゃあ、私お夕飯作らなきゃ。男所帯だからってちゃんとしたご飯食べなきゃ駄目よ。それじゃあね」
ぺこりと頭を下げ、はてどうしたものかと考える。
「金王屋は、後回しかな……」
今特に足らん物は無いだろうとゴウトが言い、其れもそうだなと返す。
「とっとと豆腐を置きに帰ったらどうだ?おれは腹が減った」
そうだなと頷き、また事務所に向き直ると鳴海が出てきた。
「あれっライドウ。今帰り?」
「そうですが、鳴海さんはまた出掛けるんですか」
そのつもりだったんだけど……と視線を手元の鍋に移す。
顔が笑っていた。
「またなんか貰ったの」
「はい。豆腐を……味噌汁にでも入れようかと」
そっかと頷き、その衣嚢からはみ出してる紙はと聞かれる。
「この間頂いた肉じゃがのレシピだそうです」
「今肉じゃがの材料ってうちにあったっけ」
どうだったかなと考える。
最近は鳴海が出掛けてばかりいたので貰った食材などを全然使っていなかった。
ので、殆ど貰い物だが大体揃ってはいる。
「あとは……肉がありません」そうかそうかと頷き、じゃあ今夜はライドウの手料理を食べようかなと言われた。
「肉は今買ってくるよ。どうせ煮るのは最後のほうだろ」
「僕の料理は美味しくないのではなかったのですか」と言う前に、じゃ、作り始めておいてねと相手は去っていってしまっていた。
仕方無しに、事務所に戻って食材を並べ、レシピを読む。
なんとなくわかった所でエプロンを身に付け、包丁を手にとった。
ライドウがしているエプロンというのは鳴海が買ってきた、腰の所で巻く物で、縁にレェスがついた女性らしい色の物である。
鳴海曰く「モダンでしょ」ということだったが、ライドウにはよく解らなかった。
ゴウトは「其れは女物だろう」と文句をつけていた。
「そういえば異世界の雷堂は割烹着だったな」
ゴウトがエプロンを見て思い出したように呟いた。
恐らく彼方の鳴海も雷堂の為に買ってきたのだろう。
鳴海について何だかんだ言っても、雷堂は結局は其れを身につけて食事の支度をするのである。
「あたたかいな……人は」
「何だ、いきなり」
ピンと耳を立てたゴウトが可笑しそうに喉を鳴らした。
「優しいし……気にかけてくれる」
「無愛想なおまえにな」
くつくつと笑い、足元に擦り寄ってきた。
「だがそんなおまえには構いたくなる何かが有るんだろうよ」
「そうだろうか」
そうは思えない。
自分は話も不得手だし、……と首を傾げる。
雷堂相手なら厭味も言えるのに。
ゴウトはするりと足元からすり抜け、「そういう所が可愛いのさ。構いたくなる」と、ソファに飛び乗った。
「さあ、早く飯を作れ。腕を上げたか味見してやる」
どうせ何時も通り不味い飯になるに決まっているがな。
ライドウは、其れもそうだなとゴウトの言葉の裏は知らずに包丁を握り直した。
肉を買いに急いだ探偵の、階段を駆け上がる音がもうすぐ聞こえてくる。