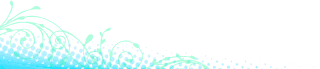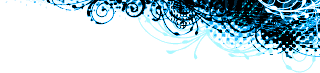
今日の献立は何にしようかと、窓の外を眺めながら頭を悩ませていた。
「雷堂」
ふいに名を呼ばれ、振り返った雷堂に触れたのは異世界の己の唇であった。
「…貴様っ」
手を振り上げ、怒鳴るのを軽くかわし、ライドウはくすくす笑っている。
「そんな、赤くならなくても」
まるで女子のようだとまた笑われ、更にむきになる。
「これは怒っているのだ!なんだって貴様はそう趣味の悪いことばかり…」
文句を言いかけて、それがまた目の前の男を悦ばせているのだとふと気づいてやめる。
「……夕食の支度をせねば」
ふん、と鼻を鳴らし、ライドウを無視して横を通り過ぎる。
異世界の己は雷堂の頭が冷えてしまったことがつまらなかったらしく、大人しく道をあけた。
割烹着をひっつかんだところで、思いついてライドウを呼ぶ。
「十四代目」
ライドウはソファに凭れて熱心にゴウトを撫でていた。
「……なにか?」
もう雷堂に興味はなくなったらしい。
顔も上げずに返事をする様子に、気分屋な奴、と思う。
「支度を手伝ってくれぬか」
割烹着を着けながら言う。
さて、どうでるか。
さっきがさっきなので、仕返しを疑って嫌がるだろうか。
ちらと窺うと、「いつもは余計なことをするなとかなんとか言うくせに……」などとぶつぶついいながらも横に来て、手を洗い出した。
なんだかんだ言って、人が好い奴。
そう思うと妙にライドウのことが可愛らしく思えて、ふ、と笑みが浮かんだ。
「……なんだ、にやけて…なにか厭らしいことでも想像しているんですか?」
厭らしい人、眉を寄せたその言葉に、そうだな、と応え、目を瞠った己に接吻けた。
「………」
硬直したまま瞬くライドウの顔がみるみる朱に染まっていくのを見て、雷堂はとうとう腹を抱えて笑いだした。
「十四代目、貴様の顔の色といったら!」
まるで女子のようだ。
そう言われて今度はライドウが怒りだす。
「なんだっ……この野郎…!この…この…は、破廉恥野郎!ばか!手伝いなんかしてやらないからな!!」
覚えてろよ、と捨て台詞も忘れず、なおも笑う雷堂を突き飛ばして、部屋に籠ってしまった。
「…破廉恥野郎はどっちなんだかな」
ゴウトが呆れ、溜め息をつく横で、雷堂、その調子だ、などと業斗がさも可笑しそうに笑っていた。