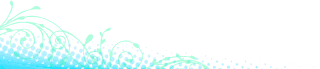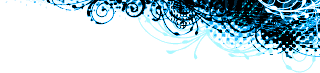
きょろきょろしながら部屋から出てきた書生に、探偵は寝ぼけ眼で応えた。
「先まで其処らに居たけど、居眠りしてる間にどっかに行っちゃった」
そうですか……、と肩を落としたライドウに、鳴海は、「最近、よくゴウトを探しているね」と苦笑いした。
ライドウと一緒に居るようになってから、今だかつて何かをこんなに探したり、気にしたりしているところを見た事がない。
「ライドウ、どうしてそんなにゴウトが気になるの」
其れに対して、聞かれたライドウ自身が首を傾げるのだから困ったものだ。
「わかりません。ただ……、最近、妙にゴウトの事を考えます」
そうして、微かに眉を寄せて苦しそうにする。
そうして、拙いながらも紡がれた心情に、思わず頭を掻いた。
「ライドウ……」
何だか、其の感情に当てはまる答えはひとつしか浮かばないんだけど。
「其れって、ゴウトの事が好きなんじゃない」
俺には其れしか考えられないな。
目を丸くしたライドウに、鳴海も目を丸くした。こんな表情の助手を見た試しがない。
「好き…………、ゴウトの事が」
俯き、まるで自分の感情を理解しようとするが如く、何度かぶつぶつ呟いた。
「其れってゴウトに恋してるって事だよ」
「恋」
まるで初めて知ったかのように瞬き、復唱する。
「此の気持ちが、恋……?」
「そう。其れはきっと恋」
ライドウは可愛いね、と顔を和ませた探偵は、「ゴウトもライドウの事が好きなんだと思うよ」と優しく告げた。
「何故、です?」
未だ恋と云う言葉の意味を理解仕切れないまま訊ねると、何でだろうねと返ってくる。
「意地悪しないで下さい」
心底困ったふうな顔をしてみせるライドウに、一寸吹き出した。
「鳴海さん」
「御免御免、……其れはゴウトに聞くと良いよ」
最近、ゴウトは前にも増して、不意にライドウの前から姿を消す。
其れは、ライドウを嫌っている訳でも困らせたい訳でも無く、寧ろライドウの気持ちを知った上でゴウトの方がどうすれば良いのか困ってしまっている様に見えた。
ゴウトに聞けと言われて、本当に然して良いのか考えあぐねる助手に、探偵は「ゴウトがよく行く場所に行って御覧。きっと居るから」と優しい声音で促した。