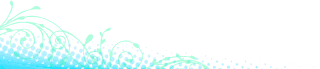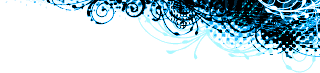
何時もならもう、鍛練に励んでいる時間だ。
その日は珍しく、ゴウトが「もう一寸ごろごろしても良いんじゃないか」などと言ったのだ。
だからこうしていた。
雨だからかも知れない。
雨の日、ゴウトは何処かだるそうな雰囲気を醸し出している。
それはゴウトが人間だったころからそうなのか、それともただ単に猫の身体の習性に引っ張られているのかは、ライドウは猫を飼ったことがないので解らなかった。
「ゴウトに聞きたいことがある」
ぽつりと口を開くと、朝から声を出していないせいかその呟きは掠れていた。
「……なんだ」
如何にも億劫な様子で、それでも耳はライドウに向ける。
「ゴウトは、何故業斗童子になったんだ」
ゴウトは特に考えるわけでもなく、さあな、と一言だけで終わらせた。
「そんな事、おまえは知らんでも良いだろう」
「でも、知りたい」
「じゃあ、教えられんな」
その飄々とした体にライドウはむっとした。
簡単に教えてくれることでは無いかもしれないけど。でも。
「そんなふうに意地悪を言わなくても良いじゃないか」
「おまえが餓鬼だからだよ」
どうにも噛み合っている気がしない会話だった。
「何時人間に戻れるんだ」
そうだなあ、と考えるような素振りをした後、わからんなあと返ってきた。
「おれがこの猫の身体でいるうちはなあ……」
ライドウは、ぱたりぱたりと左右に揺れる尻尾を眺めていた。
「では、いつか僕は人間に戻ったゴウトに、何故、業斗童子になったのかを聞くよ」
「おまえが生きているうちにはきっと戻らないさ」
ある種の確信が隠っていたが、ライドウには御構い無しのようであった。
「待つさ」
きっぱりと告げられた言葉に、ゴウトは片目だけを開けてライドウを見やった。
蒼灰の瞳は薄暗い部屋でも輝きを失わない。
「ライドウの名を還しても、この身が滅びようと……、また新しい身体に魂を移して、僕はゴウトと共に在り続ける。ゴウトは、今のおまえという業斗童子が傍につくのはこの十四代目葛葉ライドウで終りだ」
余りに自信満々に宣言するので、ゴウトが吹き出した。
ライドウはまたむっとして眉を寄せた。
「おまえ、おまえ、……本気で言ってんのか」
「僕は何時だって本気だ」
ゴウトの脇の下に手を差し込み、緩く上体を持ち上げる。
未だ笑いはおさまらないらしく、微かに身体が震えていた。
「面白いことを言うなあ。確かに葛葉の者なら出来るだろうが、そんなことを目付け役に言った奴はライドウ、おまえが初めてだ」
初めて、という単語に、ライドウの口角が僅かに上がった。
此の子供は初めての事が好きなのだ。
特に目付け役に関しての初めては大好物であった。
「だが、葛葉の御偉方は其れを許すかな?」
面白がるような口調は、ちっとも其の「御偉方」を怖れてはいないようで、ライドウはゴウトのそういう所も好きだった。
「葛葉四天王で一番の功績をあげて、必ずや」
ゴウトは面白そうに目を細めて、此奴ならあるいはやるかもな、と思う。
「ふん。本当に出来るのか見届けてやっても良い」
ライドウは益々口の端をつり上げると、「では契約の証に」とゴウトに接吻ける。
「おまえはこれがしたかっただけだろう」
ゴウトの呆れた様子も気にかけること無く、苦しい、という言葉も無視してライドウは其の胸に愛しい目付け役を押しつけた。
「僕がゴウトを迎えに来た其の時は、ゴウトから僕にして」
覚えていたらな、と返事が来たので、嬉しくなったライドウはまたゴウトに接吻けた。