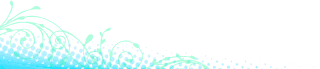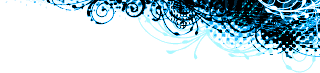
最近の此奴はどうもおかしいな。
一昨日なんて、学校帰りを迎えに行ったら急にゴウトの好きな食べ物を聞いてきた。
そして其れを買って帰り、夕飯に出してきた。
もちろんライドウにいきなりそんなことを聞かれたので、ゴウトも一寸戸惑った。
一緒に居るようになってからというものの、ライドウはこの方何かに興味を示したことなど無かったのだから……
悪いことだとは思わない。
むしろ、良いことだとさえ思うのだが、その対象がまさか自分とは思いもよらなかったのである。
いよいよもって、微かに震える白磁の指がゴウトに触れそうになる。
が、すっと引っ込んだ。
悪魔が撫でられることを夢みてやまないその指は、先刻から伸ばして引っ込むを繰り返していた。
なんだかなあ、とゴウトは思う。
触られるのは別に好きでは無いのだが、そういったことを繰り返されると、段々気の毒にすらなってくる。
触りたければ、触れば良い。
十四代目葛葉ライドウともあろう者が、目付け役に触れることもできんとは――
また伸びてはすっと引かれた指に寧ろ腹さえ立った。
「おい」
寝入っているのだと思い込んでいたらしいライドウは酷く狼狽えた様子で、一度びくりと震えた。
「……なんだ」
「おまえ、一体何がしたいんだ」
バレていた……、明らかに、ライドウが動揺している気配が伝わってくる。
「先から、指を伸ばしたり引っ込めたり、煩わしい。――そんなに、おれに触れたいか」
返事は無かったが、ただ静かにこくりと喉が鳴るのが聞こえた。
「ゴウト、ゴウト……、すまな……、」
「――良いだろう。触らせてやるよ」
え、と震えた声。
「いま、なんと?」
膝の上で握られた手は力を籠めすぎて何時もの倍白くなっている。
「触りたきゃ、触れば良いだろうと言ったんだ」
すっと立ち上がり、さてこの子供はどんな顔をしているのかと覗き込む。
そして、今にも親に叱られるのを待っていたような表情に、苦笑した。
「別に、怒ったりはしないさ。逃げも、引っ掻いたりもしない」
ゆっくりと震えながらも確実に自分に伸ばされた手を感じながら、ゴウトは目を細めた。
此奴、手に汗まで握りやがって……
ちょっとだけ可愛い奴、と思ったが、深くは考えないゴウトであった。