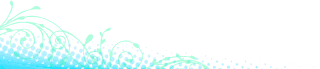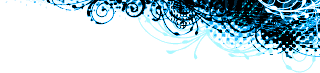
先から、部屋の中をぐるぐる歩き回っている。
そう広くもないので、直ぐに壁に当たってまた反対側へ戻る。
「嗚呼……、」
周りの者全てを虜にするほど艶かしく息をついたライドウは、どうしよう、と頭を抱えた。
ライドウには妙な癖がある。
それは、偶に耐えがたいほどくるこの衝動。
――人肌が恋しくなるのである。
里にいた頃は、森で仲が良くなった悪魔を胸に抱いたりして気を紛らせていたが、齢を重ねるごとに衝動は強くなってきている気がする。
「ゴウト……」
いつもはゴウトを抱いている。
誰彼構わないライドウの様子に心配になったゴウトが自らを宛がった。
だが、今そのゴウトは散歩にでも行ったらしく居ない。
――かれこれ15分は我慢したのだ。
もう耐えられそうに無い。
いきなり抱きつくなど、多少迷惑をかけても構わない人物……、即ち。
「あれ、ライドウちゃんどうしたの」
部屋に戻ったばかりじゃない、と不思議そうな探偵の手をとり。
「鳴海さん、立ってもらえませんか」
「え、何?何?」
手をとったまま、立ち上がった鳴海をぐいぐい壁に押しやる。
「え?え?」
そして、そのまま、ぺたりと身体を寄せた。
「どうしたの、ライドウちゃん……」
誘ってんの、という言葉には取り敢えずいいえと返し、鳴海の首もとに顔を埋めると、すうっと息を吸った。
煙草と珈琲の香りで胸がいっぱいになる。
さらにそのまま数十秒後、満たされた、と離れようとしたところ――
「ライドウ!おまえ何やってんだ!!」
ゴウトが戻ってきた。
「ば、馬鹿おまえ、おまえなあ……」
何やってんだ……と頭を垂れるゴウト。
「だって」
「言い訳なんぞ聞きたくないわ!」
毛を逆立てて、其処へなおれと怒鳴るゴウトに、だってゴウトが居なかったから……と言い訳をしながら正座するライドウの1人と1匹に、鳴海はついていけずに立ち尽くしていた。
「全く、おまえには節操だとか貞操観念とかないのか!」
「……」
ライドウはしゅんとして、俯いている。
「あの〜……、全っ然、話が解らないんだけど……」
鳴海が癖のある髪をくしゃくしゃと触りながら問う。
「此奴にはな、悪癖がある。寂しくなったら誰彼構わず抱きつくのだ。変態なんだ。とんだ阿呆なんだ!」
一応人は選んでいる、とライドウがぽつりと呟くと、五月蝿い黙れと怒鳴られてまた俯いた。
「何故よりによって鳴海なんぞに……」
「鳴海さんならまだ大丈夫かと思って」
真面目なライドウの返答に、ゴウトは一旦寝かせた毛をまた逆立てた。
「鳴海だから駄目なんだろう!おまえこんなのに抱きついたら人間駄目になるぞ。そういうのは移るんだからな」
「ひ、ひどい……ゴウトちゃん……」
「五月蝿い何がゴウトちゃんだ。どいつもこいつも馬鹿だ。馬鹿ばっかりだ!」
でもさあ、と鳴海が口を挟んだ。
「其れって、『俺以外に抱くつくな』ってことでしょ?ゴウトってば……素直に抱っこしてって言えないからって……」
「ばっ、馬鹿なに勘違いしてんだ!ふざけるのも大概にしろ!」
やだあもう、とにやにやしている鳴海に向かって怒鳴る。
と、そんなゴウトにライドウが飛びついた。
「御免ゴウト!」
抱き潰さんばかりに抱く。
「うわわわわなんだなんだ!おいこら!止めろ!苦しい苦しい!!……う」
ゴウトが段々くたりとするのも構わずに頬擦る。
「僕に抱かれたいなんて、ゴウトがそんな風に思っていてくれたなんて……、嗚呼、気づかなくて済まなかった!」
「そんな事は一言も言っておらん!」
「僕にはゴウトだけだから!」
「なんか怖いぞおまえ!」
止めろ、止めないと押し問答を繰り広げる二人を笑いながら眺め、探偵は「平和だねえ」と煙草に火をつけた。