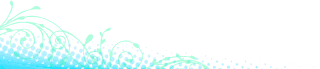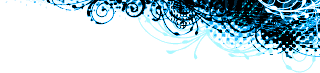
事務所に戻ると、ライドウが椅子に座って本を読んでいた。
只今戻った、と帽子の鍔を摘まみながら、雷堂は一寸緊張する。
まだ、あれからライドウとはぎこちなかったからである。
まともに話などしていない。
だから、今日に限ってまるで何事も無かったかのように振る舞うのに、戸惑った。
「昼飯ですか」
「う、うむ」
すっくとライドウは立ち上がり、外套を羽織る。
「今、食材を切らしているので……外で食べましょう。奢りますよ」
雷堂の方を真っ直ぐ見て、一寸微笑んだ。
「…………」
「…………」
ハヤシライスを奢ってもらい、さらに帰ったら食べましょうと大学芋まで買って貰い、雷堂はライドウの一歩後ろに着いて事務所への道を歩いている。
……何時、謝ろうか。
今、謝ろうか。
帰ってからの方が良いのか?
それとも、十四代目は何も言わずに此のままにするつもりなのだろうか……
……というか、奢ってもらいっぱなしだったな。
雷堂が悶々としていると、急に立ち止まったライドウにぼすりとぶつかった。
「……っ、あ、」
すまぬ、と言う前に、すみませんと言われ、瞬いた。
「僕……、貴方に酷いことを沢山言いましたし、しました。でも、これだけは知って欲しい……、あの行動は、心の底から望んでしているのでは無いのだと」
望んでしていたら其れこそ恐ろしい事なのだが、雷堂はライドウからの初めての謝罪に感動していて気がつかなかった。
「本当は、貴方の事……、好きですよ」
それだけ言うと、背を向けさっさとライドウは銀楼閣に入っていこうとする――のを、寸でのところで、引き留める。
驚いて振り返ったライドウに思いの丈を思い切りぶつけた。
「……待て。貴様だけなぞずるいではないか。我とて、我とてなあ、望んで貴様とああして喧嘩ばかりしているのではないのだ!我だって貴様の事を厭ってはおらぬ。どうだ、わかったか!?十四代目!」
今度はライドウが瞬く番だった。
恥ずかしさで、最後は殆ど叫んでいた。
はあはあと肩で息をする雷堂の肩にそっと手を置き、ライドウは心底嬉しそうに言った。
「素直になれないのは……、お互い様でしたね……」
馬鹿め、と口では言いながらも、雷堂はライドウの手に自分の手を重ねた。
「――やれやれ、やっともとの鞘に納まったか」
「然し、よくもまあ通りのど真ん中でやったもんだな」
二人仲良くビルヂングに入るのを屋上から見届けた猫達は、お帰りを言うため事務所に戻っていった。