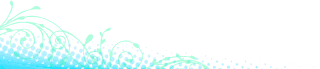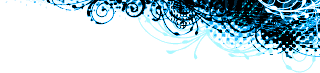
「君、料理ってできるの?」
できないなら、外食に慣れてもらうしかない。
鳴海には最初から作る気などは皆無であった。
「簡単なものなら、和食のみですが」
じゃあ作ってもらえば食費が浮くかな、なんて考えは、ゴウトの言葉によってかき消された。
「こいつの作った物は食べない方が良いぞ。食べたけりゃ、傍に付きっきりで、おまえ好みの味になるようにあれこれ言ってやるんだな」
なんで、とは聞けない空気だったので、取り敢えずはふうん、と頷いておいたのであった。
其れから鳴海は、はっきりした理由は聞かされず、また、解らないまでも、ゴウトの言葉が薄ぼんやりと解るようになる。
其れは、初めて珈琲を淹れてやったとき。
誤って砂糖を入れた方を自分に、何時もの砂糖も何も入れない珈琲をライドウに渡してしまった。
気がついた時にはライドウはもう口につけていて、「苦いものと聞いていましたが、思ったよりそうでもないのですね」と言っていた。
または、好奇心でライドウの朝食を横からつまんだとき。
それは煮物であったのだが、思わず飛び上がるほど濃い味付けだったのだ。
里の子だから、味付けが一寸普通より濃いのかな、なんて生易しいものではなかった。
「だから、やめておけと言ったのに」
ゴウトが味がまだ染みていないのではないか、というような時にはもう盛れとライドウに言っていた芋をかじりながら言った。
そういえば、ゴウトは"ライドウの皿から"何かを食べたことはない。
必ず煮物なら早くから取り分けておいてもらうし、魚なら、塩加減などいちいち口を出して自分とライドウのは別々に取り扱っている。
「ライドウは味音痴……とか?」
其れにしても酷い濃さだったが。
水を飲みながら問うと、ライドウが口を開いた。
「自分には味覚が殆どありません」
だから自然と味付けが濃くなるのです。
水に負けないくらい透明な瞳でライドウが言うので、またも、なんで、とは聞けなくなった。
一人と一匹と一緒に住んでだいぶ経った頃、ライドウの留守中にふとゴウトが聞いてきた。
「何故、ライドウの味覚が奪われたか知りたいか」
「知りたいけど、知らない方が良いことなら聞かないぜ」
ゴウトは、知っておいた方が良いのやもしれんと呟いた。
「彼奴には大抵の毒は効かぬようになっている。否、そのように造られたのだ」
何やら物騒な話に、鳴海の顔が険しくなる。
「其れって、少しずつ毒を飲んで……、とか、そういう?」
「そうだ。里でもずば抜けて優秀だった彼奴は、耐性がつけられる毒の種類も他の者よりずば抜けていた。それで葛葉の爺共は、調子に乗って彼奴に毒を飲ませ過ぎたのさ」
遠くを見たままのゴウトは、哀しそうだった。
「目付け役として会う前から俺は彼奴の事を見知っていたんだが……、その時、初めて彼奴ののたうちまわって苦しむ姿を見たよ」
結果、命は助かったが味覚が持っていかれた。
「爺共は命があるだけマシだと、ほっとしていたようだったがな」
ふん、と鼻を鳴らして、でも、遠くを見たままのゴウト。
「そっかあ……、あーあ、俺、ライドウちゃんが此処に来るって聞いてさ、里の子だから、都会の物で色々食べさせたい物とか、あったんだよな」
べたべたの、滅茶苦茶に甘い大学芋をよく作っているのを見かける。
「連れていってやれよ……、彼奴にその味はわからんかも知れんが、その気持ちは解るだろうよ」ゴウトが窓の外を見て言う。
と、階段を上ってくるライドウの靴の音がしてきた。
探偵と目付け役は、書生を迎えるために扉へ向かった。
出迎えられたことに、驚けば良い、と思いながら。