
 小さなきみとぼく
小さなきみとぼく2014/10/15
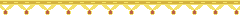
正確には初めて話した日の話です。
びびりな子闇夜さん。
気が付いたら知らない建物の中にいて、痛かった所が全部治療されていて、ついさっきまで一人だったのに沢山の人に囲まれていて。
自分の置かれた状況の目まぐるしい変化に上手く対応しきれない。
ただそこにいた大人達の話から自分が「保護」された事だけは理解出来た。
生活は一変した。
強制的にさせられていた洗濯も、炊事も、掃除も、何もかもやる必要が無くなった。
代わりに与えられたのは、遊びや、お昼寝や、お菓子。
思わず施設の人に「僕は何もしなくていいんですか?」と尋ねると、「いいんだよ」と優しい笑顔で頭を撫でられた。
そんな笑顔を向けられた事も頭を撫でられた事も無かったから、彼は更にビックリして呆然とその言葉に頷くだけだった。
でも、突然与えられた自由は逆に扱いが難しくて。
しかも彼はこっそりと怖がられているようだった。
同じように保護された子供達。
その年齢は同年代だったり年上だったり年下だったり、まちまちなものだ。
彼らの大多数が、新入りの右目を怖がる。
運ばれてきた時から彼の右目は失われていた。
余りに傷が酷かった為、治療された後の傷痕も痛々しい物になっていた。
普段は包帯をしているが、それでも幼い子供達にとっては十分恐怖心を煽るものらしく、露骨に彼を避ける者までいた。
闇夜はそれを余り気にしていない。
周りが自分を怖がる理由も分かるから、「あぁ、やっぱり怖いよね」程度に思って自分からも極力周りに近付こうとはしなかった。
そもそも彼は一人が当たり前だったので、避けられたところで何となく相手への罪悪感が残るのみだった。
寂しいとは思わなかった。
実をいえば、彼も彼で怖かったのだ。
一人が当たり前だった彼からすると、他人との接触とはまさに未知の体験だったから。
皆に怖がられる原因である右目もコンプレックスになった。
いつしか彼は部屋の隅の方で絵本を読む事が日常になっていった。
「ねぇねぇ」
その日常がある日突如として壊された。
いつものように絵本を読んでいると親しげな呼び掛けが聞こえた。
最初は自分が呼ばれたわけじゃないだろうと無視していたが、再度、更に近い所から呼び掛けられて心底ビックリしてそちらを見た。
いつの間にやら左目側に赤い髪の男の子がしゃがみこんでいた。
「なっ、…な、何ですか…?」
驚きすぎて持っていた本が手から転がり落ちた。
ひっくり返った声で尋ねながらじわじわと後退する。
しかしそれはすぐ傍に置いてあった本棚によって阻止されてしまった。
小さな背丈に見合わぬ大人用の黒いマフラーを巻いた男の子は、彼のそんな怯えきった様子にへらっとした笑顔を見せた。
笑いかけられた側は俯く。
「そんなこわがらなくても大丈夫だよ!おれ、きみと友達になりたいだけだもん!」
「へ……と、友達…?」
「うんっ、きみいっつも一人で本よんでるでしょ?さびしくないの?」
「……いえ…別に、さびしくはないです」
「えー、へんなのー」
何故初対面の相手に変なの呼ばわりされなくてはいけないのか。
悪気は一切無いらしい赤い髪の子は不思議そうな顔で小首を傾げた。
青い瞳が興味津々といった様子で闇夜を見ている。
俯いていても分かるその視線が彼にとっては怖かった。
人に興味を抱かれ、近付かれるのが恐ろしい。
極度の人見知りと言ってしまえばそれまでだが、彼には右目の傷という確かなコンプレックスがあり、照れなどという可愛らしい感情は少なかった。
その為、今もこの状況をどう切り抜けるかという事ばかり考えている。
「でも、じゃあいつも一人なのは、一人がすきだから?」
「え…、…まぁ、すきってわけでもないですけど…」
それは本心だ。
この傷が無ければまだマシに人付き合いもしていただろうし、友達という絵本でばかり見る単語に相当する相手も出来ていただろう。
でも現実は上手くいかないものだ。
他人と距離をおく事を決めたのは自分だが、それは周りを怖がらせたくないからだ。
好きで出来た傷じゃない。
好きで陥った現実じゃない。
「そうなの?ならどーして一人でいるの?」
「………みんな、怖がるから」
「こわがる?何を?」
「…これを」
言って右目の包帯に触れる。
赤髪の子はきょとんとした。
それの何がこわいの?、と心の底から不思議に思っている様な声音で聞く。
闇夜は我が耳を疑った。
何を言ってるんだこの子。
ここに来て俯くのをやめ、ようやく相手の顔をまともに見た。
そんな些細な事でも赤髪の子は「やっと目が合った」と嬉しそうだ。
その表情に闇夜への恐怖心は微塵も無い。
そもそも怖がっていたら話し掛けてなどこない筈だ。
「み、右目……僕の右目、ないんだよ?きもちわるいケガしかないんだよ?」
「ふーん」
ふーん。
未だかつて、この傷をそんな一言で流された試しは無い。
施設の大人ですら気を遣ってあまり触れようとはしない話題。
それを、目の前の男の子は実に無関心に流した。
腫れ物を扱う様な対応を予想していた闇夜は残された左目を丸く見開いた。
「…こわくないの?」
「だから何が?きみの右目なんかちっともこわくないよ」
それは、ある意味闇夜が一番欲しかった言葉かもしれない。
怖がられるのも、嫌に親切にされるのも、虚しくて仕方なかった。
普通に接してほしかった。
こんな傷なんて存在しないかのように。
そこにきて、赤髪の子はまさにその対応だった。
傷痕になんて一切関心を抱いてない。
言い方が乱暴になるが、彼の傷などどうでもいいとすら思っていそうだ。
その子はまたへにゃりと破顔する。
「おれはケガとおしゃべりしたいわけじゃないもん。きみとおしゃべりして、なかよくなりたいっ」
「………、…」
「…だめ、かな?」
不安そうな顔をする男の子に言葉が出ない。
その代わりとばかりに、赤い隻眼からぼろぼろと涙が零れだす。
わぁ!だ、大丈夫?、と驚き慌てる相手を余所に、泣いている本人は小さく笑いを漏らした。
場にそぐわぬそれに男の子が固まって頭上に疑問符を飛ばす。
その様子に笑いは更に増大した。
「っあははは!はっ、はははは、ふふっ……ご、ごめ…ごめんなさい…ははは…、ビックリしてるあなたの顔が、おもしろくて…」
「えぇー!おもしろくないよ!それにきみがいきなり泣きだしたからビックリしたんでしょう?」
泣きながらお腹を押さえて笑う彼に頬っぺたを赤くして反論する。
ムキになって言い返す辺り何となく年下なのかもしれない。
微笑ましい気分になりながら口を開く。
「ふふふ……だって、うれしかったから」
「え?」
「ケガじゃなくて、僕を見てくれてるのが」
「そりゃそうだよっ、おれたち友達だからね!あ、おれはいせっていうの。きみは?」
どうやら彼の中では既に闇夜は友達という事に決まったらしい。
しかし、闇夜にそれを否定する気は無かった。
だから、まだ僅かに涙を目元に浮かべた笑顔で答えた。
「…僕は、やよっていいます。よろしくね、いせ君」
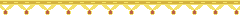
戻る
