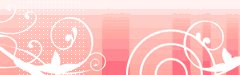猫パロ(5)
猫パロ(5)2014/10/20
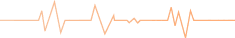
前回の続き。
とりあえずの措置にと双子を自室に隔離してから、枯雲は改めてお茶を淹れて持ってきた。
リビングのソファにはがいを膝に乗せた伊勢が座っている。
運ばれてきた紅茶の香りにがいは少し鼻をひくつかせたが、すぐに興味を失ったのかテーブルから顔を隠す様にして丸くなった。
シュークリームの皿と紅茶をテーブルに置き伊勢の隣に座った枯雲が、また申し訳なさそうに謝った。
「…本当にごめんよ伊勢君」
「あははは、もー、大丈夫ですってば。ちょっと過激にじゃれられただけですよ、気にしないで下さい」
それより、ほら、食べましょう!
元気良く促し、自らもシュークリームを手に取る。
事故とはいえ自分の不注意により生徒に痛い思いをさせてしまった枯雲は、中々気持ちを切り替えられない。
だがいつまでも落ち込んで来客に気を遣わせるのも悪いと思い直し、伊勢に倣ってシュークリームを手にした。
いただきます、と呟き一口かじる。
「!、すごい…シュー生地ふわっふわだね」
「でしょ?此処のシュークリームは何か特別な方法で作ってるらしくて、すっごく美味しいんですよっ」
「へぇー、今度僕も行ってみようかなぁ」
甘味好きな彼の気分は柔らかなシュー生地によりいくらか明るくなった。
その様子に内心ホッとしながら、伊勢もシュークリームにかじりつく。
口内を満たす甘味に表情が綻ぶ。
すると、シュークリームに興味を抱いたらしいがいが起き上がり、みぃと鳴いた。
『伊勢、それ何?』
「あ、ごめんねがい。これはがいにはあげられないんだ」
『?、なんで?』
小首を傾げてみゃあみゃあと声を上げる。
伊勢からシュークリームを奪うつもりなど毛頭無いのだが、子猫特有の好奇心というものも抑えられないのだ。
大変可愛い様ではあるが、これに負けているようでは飼い主は務まらない。
駄目なものは駄目だと分からせるのも生き物を飼う者の役目だ。
「えーっと、がい君だっけ?お腹空いてるのかな?」
「いや、ただちょっとシュークリームが気になるだけだと思います。この子少食だし」
「そっか。あ、ねぇねぇ、その子少し抱っこしてみてもいいかな?」
伊勢とがいのやり取りに加わった枯雲が控えめに申し出る。
伊勢は二つ返事で了承した。
そもそも今日此処に来たのは互いの猫を見せ合う為だ。
断る理由など無い。
「いいですよー。ちょっと待って下さいね…」
食べかけのシュークリームを皿に置いて、膝のがいを抱き上げる。
「み?」
「ほら、枯雲教授だよー。俺の通ってる大学の先生」
言いながら小さな白い塊を枯雲の腕の中に移した。
がいを受け取った枯雲は、手のひらで感じる毛並みの柔らかさに目を輝かせた。
「うっわぁー、凄い!もふもふだねぇー、可愛いなぁ。うちの子達よりちょっとだけ小柄で、ぬいぐるみみたい。あ、この子オッドアイなんだね。綺麗だなぁ」
休む事のない口をそのままにしながら、頭や顎や背中を撫で続ける。
他人の飼い猫と触れ合う機会が少ない為か、分かりやすくテンションが上がっている。
伊勢は伊勢で、家族同然の存在を褒められるのは気分が良く、嬉しそうに相槌を入れていた。
一方、撫でられている張本人であるがいは、どこか不満そうに尻尾を揺らしている。
毛を逆立てるといったあからさまな拒否反応は見せていないが、現状を面白く思っていないのは事実だった。
『……知らない人…やだな…』
捨てられた過去を持つ彼はその経験上、常に人間に対して一定の疑心を持つようになった。
飼い主である二人を除き、それ以外のありとあらゆる人間が苦手なのだ。
場合によっては先程の双子の様に唐突な攻撃に打って出るくらいには、人間という生き物が嫌いだ。
見知らぬ他人に触れられ、撫でられるなど耐えられない。
今は相手が伊勢の知り合いという事で少しばかりの辛抱をしているのだが、本心から言えばもう離してもらいたい。
どれだけ優しく撫でられたとろこで全く気持ち良くない。
不意に枯雲の手が腹という弱所に伸びてきて、とうとう耐えきれずにがいは「しゃっ!」と短い威嚇を漏らした。
「わわっ」
同時に繰り出した猫パンチが、腹に伸ばされかけていた枯雲の手をはたき落とす。
爪を出していなかったのはがいなりの最大限の良心だ。
「あ、コラがい!」
「大丈夫大丈夫、パンチされちゃっただけだから。それに、悪いのは慣れてもいないのにいきなりベタベタ触った僕なんだ。ごめんね、がい君」
逆上するわけでも無く素直に自らの非を詫びる枯雲に、がいは少なからず好感を抱いた。
しかしやはり苦手なものは苦手で、さっさと彼の腕から抜け出し伊勢の膝へと駆け戻る。
安心しきった様子で飼い主にくっつくその様子に、枯雲は小さく笑った。
「伊勢君の事が大好きなんだね」
目に見えて分かる事実を口にすると、伊勢がやや照れ臭そうにはにかんだ。
がいは再度体を丸め、膝の上に置かれていた伊勢の左手にじゃれついた。
甘噛みを繰り返してくる子猫に片手だけで応対しながら、「それを言うなら」と話題を転換させる。
「双子君こそ、教授の事が大好きみたいですよ」
枯雲に粗相を怒られていた黒猫達の様子を思い出し、くすくす笑いが漏れる。
伊勢に対してはあれだけ攻撃的な姿勢を見せていた双子が、枯雲の怒声一つで勢いを失っていた。
しょんぼりと耳を垂らすその姿は叱られた子供の様だった。
枯雲の事が好きだからこそ、叱られたショックも大きかったのだろう。
微笑ましく思う伊勢に枯雲はやや曇った笑顔を見せる。
「うん……まぁ、僕を慕ってくれるのは凄く嬉しいよ。僕も彼らの事が大好きだしね。…ただ、よその人にももう少しだけ愛想良くなってくれたらなぁ…って思っちゃうんだ」
せめていきなりお客さんに襲い掛かる様な真似はさせないようにしなきゃ。
呟いた枯雲が、何か妙案は無いかと伊勢に尋ねる。
肩によじ登ってきたがいを撫でながら伊勢は少し悩む素振りを見せた。
伊勢が飼っている猫はがいだけであり、そのがいはあまり手の掛からないタイプだ。
拾ってきたばかりの頃こそよそよそしかったが、襲い掛かられた経験は無い。
よって、双子の様な少しやんちゃが過ぎるタイプのしつけ方を伊勢はあまり知らないのだ。
「うーん、そうですねぇ……試しにもっと身近な他人と遊ばせるとかどうです?」
「身近な他人?」
「はい。俺は教授の生徒ですけど、それって双子君からすればかなり遠い存在だと思うんですよ。だからもっと近い関係の人と交流を図って、人間が無害だって事をまず知ってもらうんです」
「…なるほど」
要は慣れだと言いたいのだろう。
枯雲は神妙な顔で頷いた。
「あと、さっき思い出したんですが、俺この前道端で双子君と会ってたんですよ」
「え、そうなの?」
「はい。何かがいと揉めてたみたいで…。だから、喧嘩相手の飼い主である俺に攻撃的なのはある意味仕方ないと思います。…あ、俺が乱入したせいで喧嘩はおじゃんになってたから、がいも双子君も怪我は無かったですよ」
自らの飼い猫が預かり知らぬ場で危険な振る舞いをしようとしていた事を知り固まる枯雲に、伊勢は慌てて付け加える。
その報告を聞いて安堵の息を吐いた枯雲は「良かった」と呟いた。
双子達の奔放な性格はよく分かっているので、散歩に出せばきっと少なからず冒険はしているのだろうと踏んでいた。
が、まさか人様の、それも教え子の飼い猫にあわや怪我をさせる所だったとは知らなかった。
どこをほっつき歩いているかも分からない猫同士の喧嘩をいちいち止める事など不可能だが、それでも枯雲は心を痛めた。
「そっか……同じ猫相手でもそんな調子なんだ…。これは一刻も早く何とかしないと」
実は双子は人見知りでも何でもなくただ単に枯雲至上主義なだけなのだが、そんな事実など本人には伝わっておらず、枯雲は先程伊勢から聞いた対策法を実行してみる事にした。
近い関係の他人に心当たりがあるのだ。
小さなあくびを漏らすがいを肩に乗せたままの伊勢が、興味本意で誰なのか尋ねる。
いつの間にか一欠片程の小ささにまでなっていたシュークリームを口に放り込み、枯雲は笑って答えた。
「実はね、双子君は人から貰った猫なんだ」
「へぇ、そうなんですか。あ、じゃあ、近い他人って…」
「うん、僕に双子君を譲ってくれた人を近々呼んでみる。……ただ、ね」
「?」
枯雲に倣いせっせとシュークリームを食べる伊勢は、煮え切らない枯雲の態度に首を傾げた。
肩にいる事に飽きたらしいがいがぴょんと膝に着地した。
だいぶ冷めた紅茶を啜り、苦笑いとおぼしき引きつった顔で枯雲は明後日の方向を見る。
やがて、喉に小骨が刺さった様な声で「…その人、ちょっと怖いんだ」と告げた。
この教授が誰かを怖がる姿など見た事が無かった伊勢は、意外に思いながらも「あ〜…」と同情めいた感嘆を漏らした。
白い子猫だけが、我関せずとばかりにのんきなものだった。
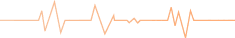
戻る